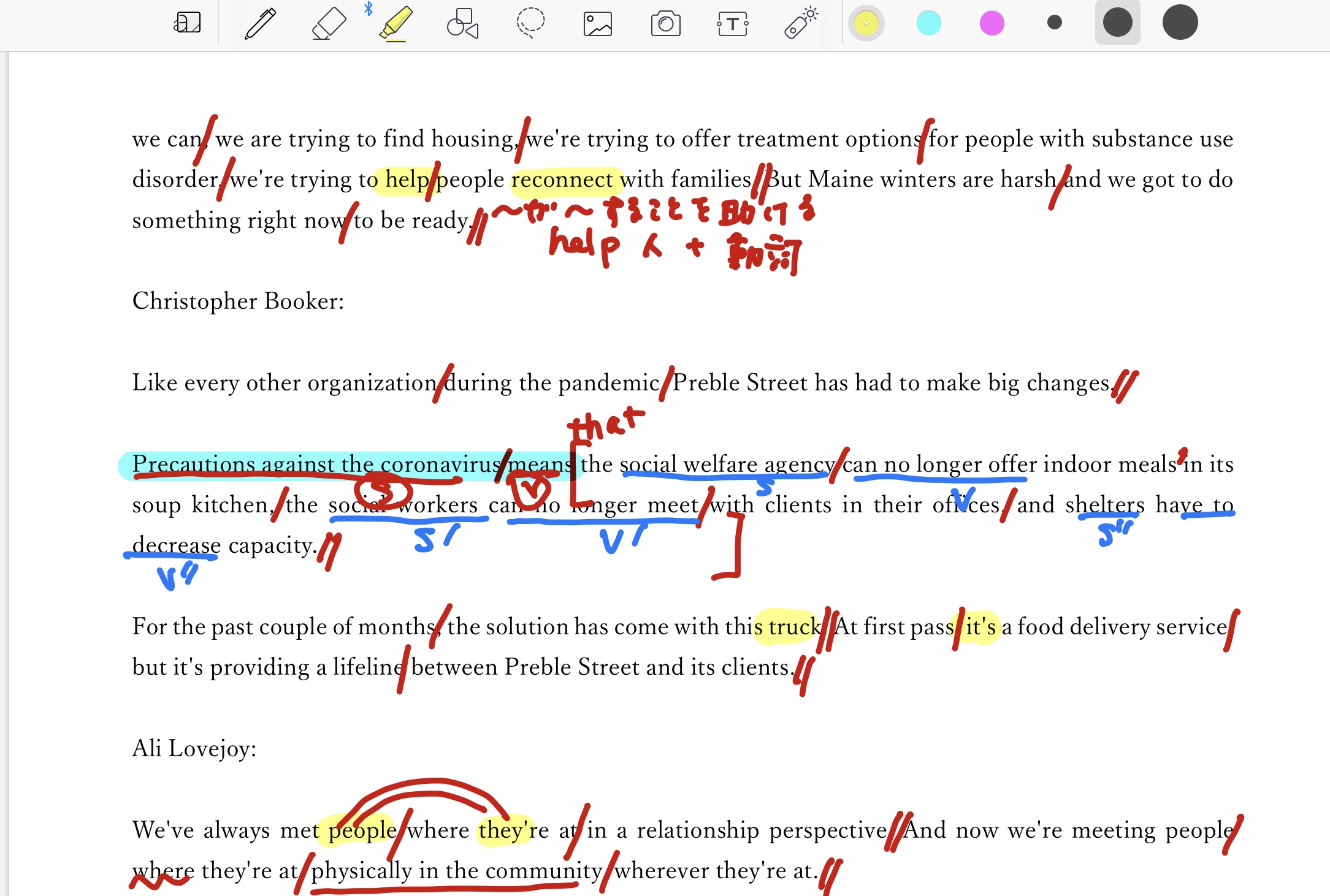箱根駅伝を描いた三浦しをんの名作。私はこの本がとても好きで、心理療法研究会で知り合った仲間が主催している音読の会では何度もこの本からの一節を読んでいる。
ほぼ陸上の素人集団が箱根駅伝の予選会どころか本選でシード権を獲得してしまうという、かなり荒唐無稽な物語ではあるのだが、陸上が好きだけれども「陸上に選ばれなかった」者の思いや、走ることそのものが生きることであり、喜びである者が体験する心の世界がうまく描けていると思う。
特に、「走るために生まれてきた」ような主人公の天才少年、蔵原走(くらはら かける)が体験する”ゾーン”の描写は圧巻だ。
(前略)走が戦うべき相手は、目に見える選手ではなく、時間だった。形のない時間というものをたぐり寄せなければならない。寛政大が、ひとつでも順位を上げるために。走が、いま自分にできる最高の走りを、箱根駅伝の歴史に刻みつけるために。
四車線になり、視界が広がったせいでスピード感が違ってくる。走っても走っても、なかなかまえに進めていないような気がする。あせるな、と言いきかせ、走は水を口に含んだ。俺は大丈夫だ。もっと行ける。筋肉がちぎれそうに叫んでいる。加速しろ。限界を超えた、その先へ。
ボトルを道端に投げ捨てる。冷たい液体が、体内をすべり落ちた。
「あ・・・」
走が思わず発した声は、掠れてだれの耳にも届かなかった。
体の底で、なにかが鋭く破裂した。一点で弾けた力が体じゅうに、指の先まで拡散していく。拡散ではなく、集合しているのか? エネルギーの流れがあまりにも早すぎて、どちらなのか区別がつかない。
音が一気に遠のき、脳髄が冴え渡った。走る自分の姿を、もう一人の自分が俯瞰しているみたいだ。呼吸が急に楽になった。舞い散る雪片のひとつひとつが、ひどく鮮明に視界をよぎる。
なんだろう、この感覚。熱狂と紙一重の静寂。そう、とても静かだ。月光が指す無人の街を走っているようだ。行くべき道が、ほの白く輝いて見える。
このまま還ってこられなくなりそうなほど、気持ちがいい。怖いぐらいだ。輝く恒星のほうへ、たった一人で押し流されていく(後略)。
(『風が強く吹いている』「十(最終章) 流星」より)
この描写は、確かにゾーン状態を作家が取材して書いたものではあるのだろうけれど、実際にこういうことが起きているのではないかというリアリティに富む。荒唐無稽なプロットではあるものの、陸上をやっている人にファンが多いというのも、こういう心理描写などがよく取材されており、真に迫っているからなのかもしれない。
そして、スポーツを描いた文学作品の”ゾーン状態”の描写は共通性がある。例えば、松本大洋の『ピンポン』で、主人公のペコ(星野裕)と強敵ドラゴン(風間竜一)の試合におけるドラゴンの心理描写。
全身の細胞が狂喜している。
加速せよ、と命じている。
加速せよっ・・・
加速せよっ・・・
目には映らない物、
耳では聞こえない音、
集中力が外界を遮断する。
膨張する速度は静止に近い。
奴は当然のように急速な成長を遂げる。
反射する頭脳、瞬発する肉体・・・
しだいに引き離されていく・・・徐々に置いてゆかれる感覚。
優劣は明確。
しかし、焦りはない。
全力で打球している。
怯える暇などない。
松本大洋『ピンポン』第五巻 第50話 Fly より
このシーンは窪塚洋介が主演した映画でも秀逸な場面で、そこに挟まれる鳥のカットが非常に印象的。解き放たれたのは、「勝たなければならない」というドラゴンの強迫感か、あるいは別のものか。
「静止」と「スピード」という、一見対極にあるような二つのものが同時に感じられるというのも興味深い。三浦しをんも、松本大洋も、スポーツとは違うけれど、ものを「書く」という過程で同じような出来事を体験しているからこそ、ゾーンの描写が説得力のあるものになっているかもしれない。